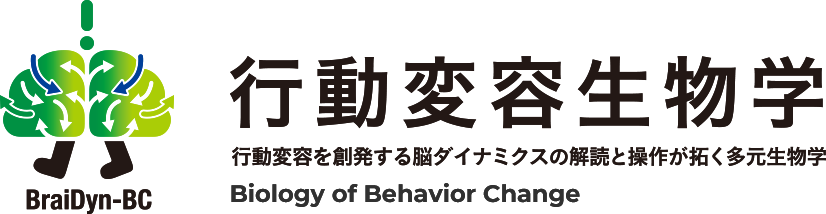第17回 ・第18回「Computational Neurology Club Seminar」開催のご案内(『行動変容生物学』共催)
中江です。7/28と8/4に栗川知己先生(公立はこだて未来大学)と南部篤先生(生理学研究所)に以下の講演をハイブリッドで行って貰う予定です。こちら、参加のほどよろしくお願いします!
第17回 Computational Neurology Club Seminar
テーマ: 自発的神経活動の機能的な意義:特に学習との関係について
日時:2025/7/28(月)15:30-17:00 JST
開催場所:ハイブリッド(名古屋大学・鶴舞キャンパス、Zoom)
講演者:栗川知己(公立はこだて未来大学)
概要:近年神経科学において、自発的な神経活動に注目が集まっている。入力がない神経活動は様々な時空間パタンを示すだけでなく、刺激や入力が与えられたときにどのような振る舞いをするか=機能的な意義とも深く関係している。例えば、自発的な神経活動の空間パタンと学習するパタンの幾何学的な関係性が、どのように学習がすすむかとも関係している。本発表では、そのような自発的な神経活動の機能的な意義を紹介した後に、最近行っている自発活動と学習との間になりたつ一般的な関係や、その周辺の研究をお話したい。
第18回 Computational Neurology Club Seminar
テーマ: 大脳基底核の機能と病態生理の統一的理解を目指して
日時:2025/8/4(月)13:00-14:30 JST
開催場所:ハイブリッド(Zoom、福井大学総合研究棟I 4階知能システム演習室)
講演者:南部篤(自然科学研究機構生理学研究所)
概要:正常なサルやマウスにおいて、大脳基底核の出力核である淡蒼球内節・黒質網様部から神経活動を記録し、大脳皮質運動野に電気刺激を加えると、早い興奮・抑制・遅い興奮から成る3相性の応答が引き起こされる。早い興奮・抑制・遅い興奮は、それぞれハイパー直接路・直接路・間接路を介した応答であり、この3経路が時間・空間的に適切に働くことが随意運動の遂行に必須であると考えられる。パーキンソン病、ジストニアなどの大脳基底核疾患モデル動物から記録を行うと、この3相性の応答パターンが系統的に変化していた。また、定位脳手術を施すと応答パターンが復活し、運動も正常化した。大脳皮質に由来する大脳基底核の動的な活動の変化を基に、大脳基底核の機能、大脳基底核疾患の病態生理や治療メカニズムを統一的に考えてみたい。
ご登録は以下のリンクから可能です。